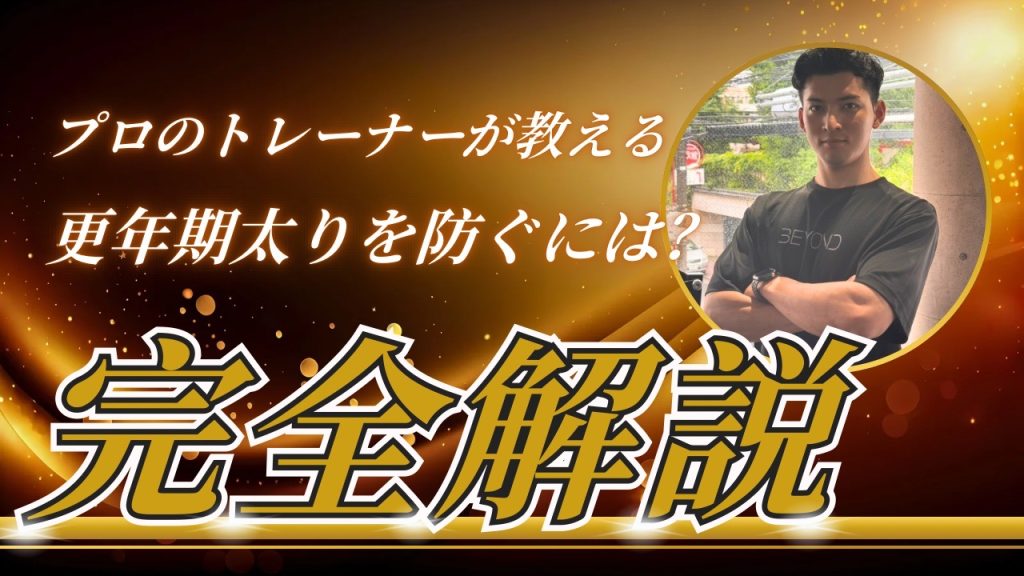更年期太りを防ぐには? 徹底解説
BLOG
2025 / 08 / 11
最終更新日:2025年8月29日
ホルモンの変化や加齢による体組成の変化で「いつのまにか体重が増えた」「お腹周り(内臓脂肪)が目立ってきた」と感じる女性は多いです。
ここでは科学的根拠に基づいた対策を、すぐに実行できる形で解説します。
なぜ更年期に太りやすいのか(原因)

更年期(一般的に閉経前後の数年間)には、卵巣からのエストロゲン分泌が低下します。
エストロゲン低下は脂肪の分布を変え、下腹部(内臓脂肪)が増えやすくなること、そして筋肉量の減少(サルコペニア的変化)により基礎代謝が下がることに関係しています。
加えて睡眠障害・気分の変動・生活活動量の低下などの要因が重なり、体重増加を招きます。
- ホルモン変化:エストロゲン低下による脂肪分布の変化(お腹に脂肪がつきやすくなる)。
- 筋肉量の減少:筋肉が減ると基礎代謝が下がり消費カロリーが減る。
- 生活因子:運動量低下、睡眠不足やストレスによる過食、アルコールや間食の増加。
自分の現状を確認するポイント
対策を始める前にまず“現状把握”をしましょう。
測るべきは体重だけでなく、体組成(筋肉量/体脂肪)、ウエスト周囲長、運動習慣、睡眠、飲酒量、ストレスレベルです。
- 体重とウエスト(へそ周り)を定期的に測る
- 家庭用体組成計で筋肉量と体脂肪の傾向を見る(変化を重視)
- 食事日記を1〜2週間つけて傾向を把握
- 週の身体活動量(歩数・運動時間)を評価
食事でできる対策(基本と具体例)

更年期の体重管理は「極端な食事制限」ではなく、栄養バランスを保ちながら総カロリーを適正にすることが大切です。
最近の研究や専門団体も、地中海食に近いバランスの良い食事を推奨しています。
基本の4ルール
- たんぱく質を意識して摂る:筋肉量維持のために、1食あたり卵1個分〜鶏胸肉等を含む20〜30g目安を意識。
特に朝と運動後に。 - 野菜・食物繊維を増やす:血糖の急上昇を抑え満腹感を持続。全粒穀物や豆類を取り入れる。
- 加工食品・糖質(特に液体の糖)を減らす:間食のスナックや甘い飲み物は総カロリーを押し上げやすい。
- アルコールを節度ある量に:飲酒はカロリー源であり、代謝や睡眠にも影響する。
1日の食事例(参考)
朝:ヨーグルト+フルーツ+オートミール少量+ゆで卵(たんぱく質)
昼:全粒パンor玄米+魚・鶏などの主菜+たっぷり野菜サラダ+オリーブオイル少量
間食:ナッツ一握り、低糖のプロテインバー、ヨーグルト
夜:野菜中心の副菜多め+豆や魚中心の副菜+ご飯は控えめ(80〜120g)
ポイント:急激な極端な糖質カットよりも、総カロリー管理と質の良い脂質・十分なたんぱく質の確保が長続きしやすいです。
運動:有酸素+筋力トレで代謝を守る

更年期の体組成悪化(筋肉減少・内臓脂肪増加)には、筋力トレーニングを中心に据えることが有効です。
週に2〜3回のレジスタンストレーニングと、週150分程度の中強度の有酸素運動が推奨されます。
筋トレは基礎代謝維持と体脂肪減少の両面で効果的です。
実践プラン(初心者向け)
- 筋トレ(週2〜3回、45分程度):スクワット、プッシュアップ(膝付き可)、プランク、ラットプルダウンやダンベルローなど。1セット8〜12回を2〜3セット。
- 有酸素(週3〜5回):速歩・ジョギング・サイクリングなど、合計で週150分以上を目安に。
- 日常の活動量を増やす:こまめに立つ、階段を使う、歩数を増やす(まずは1日7,000〜8,000歩を目標に)。
始める前に持病や不安がある場合は医師に相談してください。
筋力トレのフォームはケガ予防のため指導を受けることを推奨します。
睡眠・ストレス管理も無視できない

睡眠不足や慢性的なストレスは食欲ホルモン(グレリン・レプチン)を乱し、過食や間食傾向を強めます。
良質な睡眠(7時間前後)を確保し、リラクゼーション(深呼吸・マインドフルネス・軽い運動)を習慣化しましょう。
夜のカフェインやアルコールは睡眠を妨げるため注意が必要です。
ホルモン療法や薬の役割(医師と相談する場面)
ホルモン補充療法(HRT)は更年期症状(ほてり・睡眠障害など)を和らげるための有効な選択肢であり、いくつかの研究では体脂肪分布の変化を抑える効果も示唆されています。
ただし全ての人に適するわけではなく、リスク(乳がんや血栓症など)を含むため、専門医と利点・欠点を十分に話し合って判断することが重要です。
生活習慣改善が第一選択ですが、生活で改善が難しい症状(重度の不眠、うつ症状、強いほてりなど)がある場合は医療介入を検討します。
更年期太りを防ぐための習慣とポイント

更年期はホルモンバランスの変化で体が敏感になりやすく、普段の何気ない習慣が体重増加につながることも。
ここで、特に注意したい習慣と改善策をご紹介します。
- 夜遅い時間の食事や間食:消化が遅れ脂肪蓄積のリスク大。夕食は就寝3時間前までに済ませるか、軽めに。
- 運動不足で座りっぱなしが多い:筋肉量低下・代謝ダウンを招く。30分に1回は立ち上がり軽いストレッチを。
- アルコールを毎晩摂る:カロリーオーバーと睡眠質の低下に繋がるため週2〜3日に抑える。
- ストレスの過剰蓄積:過食や睡眠障害の原因。趣味やリラックス時間を定期的に設ける。
- 水分不足:代謝や便通が滞る。1日1.5〜2リットルの水分補給を意識。
これらの習慣を見直すだけでも、体重管理に大きな効果が期待できます。
まずはできそうな1つから取り組んでみましょう。
更年期におすすめの簡単ストレッチ&ケア法
更年期は筋肉の硬さや血流の低下も気になるポイント。
日常に取り入れやすいストレッチやケアで、代謝アップやリラックス効果を高めましょう。
- 腰回りのストレッチ:椅子に座って腰をゆっくり左右にひねる。血流促進と腰痛予防に効果的。
- 肩甲骨まわりのほぐし:両肩を上げ下げする運動を繰り返し、肩こり緩和と姿勢改善に。
- 深呼吸+腹式呼吸:リラックス効果が高く、ストレス軽減に役立つ。
- お風呂での半身浴:血行促進と疲労回復におすすめ。温度はぬるめ(38〜40度)が◎。
1日5分の習慣でも効果は積み重なります。ぜひ毎日の生活に取り入れてみてください。
更年期太り対策に必要な「正しいマインドセット」
更年期の体重管理は短期的な結果にこだわりすぎず、長期的に少しずつ生活習慣を改善していくことが大切です。
焦らず自分のペースで取り組むことで、心身の健康を維持しやすくなります。失敗しても落ち込まず、「できたこと」に目を向けるポジティブな姿勢が継続の鍵です。
また、周囲のサポートや専門家の助言を積極的に活用することも効果的です。
水分補給
更年期はホルモンバランスの変化で体の水分保持能力が低下しやすいため、意識的な水分補給が大切です。
1日に1.5~2リットルの水をこまめに飲むことで代謝を促進し、むくみや便秘の予防にもつながります。カフェインやアルコールは利尿作用があるため、水や麦茶、ハーブティーなどを選ぶと良いでしょう。
すぐ始める!7日間の実践プラン(例)
下は「まず挑戦してみるため」の短期プランです。
習慣化のコツは出来るだけ簡単にし、継続できるレベルから始めること。
DAY 1:朝散歩30分/たんぱく質豊富な朝食/夜は野菜中心 DAY 2:自宅で筋トレ(下半身メイン30分)/間食はナッツ DAY 3:速歩40分/炭水化物は全粒を選ぶ DAY 4:筋トレ(上半身+コア30分)/睡眠ルーティン強化(就寝前1時間はスマホオフ) DAY 5:軽い有酸素(自転車等30分)/食事は地中海式を意識 DAY 6:フル休養 or 軽ストレッチ+ヨガ/アルコール控えめ DAY 7:長めのウォーキング60分/1週間の振り返り(体重・ウエスト確認)
7日後、続けられそうな項目を2〜3つ選んで「年間の習慣」に落とし込むと効果的です。
更年期の体調変化と体重管理の関係

更年期はホットフラッシュや気分の変動、疲労感など体調の変化が多い時期です。
これらの症状が日常の食事や運動習慣に影響し、結果的に体重管理が難しくなることがあります。
- ホットフラッシュ(のぼせ・発汗):睡眠障害や疲労を引き起こし、運動量低下に繋がる場合がある。
- 気分の波・イライラ:ストレスによる過食や間食の増加を招きやすい。
- 疲労感・体力低下:積極的な運動を避けがちになり、筋肉量減少を加速させるリスク。
症状を軽減するための生活習慣改善や医療相談も大切です。
自分の体調に合わせ無理なく続ける体重管理を心がけましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. ホルモン療法で必ず体重が減りますか?
A. ホルモン療法は更年期症状を和らげたり、脂肪分布の変化を軽減する可能性がありますが、単独で大きな減量効果を期待するものではありません。
生活習慣の見直しと併用して考えましょう。
Q. 筋トレを嫌いでも効果はありますか?
A. 歩行や日常動作(階段を使う等)でも活動量を増やせば効果はありますが、筋トレを取り入れると筋肉量を効率的に維持でき、代謝低下対策としてより有効です。
Q. サプリや特定の食品で予防できますか?
A. 特定の“魔法の食品”はありません。
全体の食事パターン(たんぱく質豊富・野菜中心・加工食品を減らす)が重要です。
必要ならDHA/EPAやビタミンDなどを医師と相談の上で補助的に検討します。
まとめと行動のすすめ
更年期太りはホルモンの影響だけでなく「筋肉量低下」「生活習慣の変化」が重なって起きます。
対策のコアは (1)たんぱく質を中心とした栄養、(2)筋力トレーニング中心の運動、(3)睡眠とストレス管理、(4)必要なら医療(HRTなど)を専門医と検討 することです。
まずは小さな変化(歩数を増やす、朝のたんぱく質を増やす、週2回の簡単な筋トレ)から始めてみましょう。
本記事の著者

BEYOND武蔵小杉店トレーナー
竹内陸
BEYOND武蔵小杉店では無料体験受付中です!