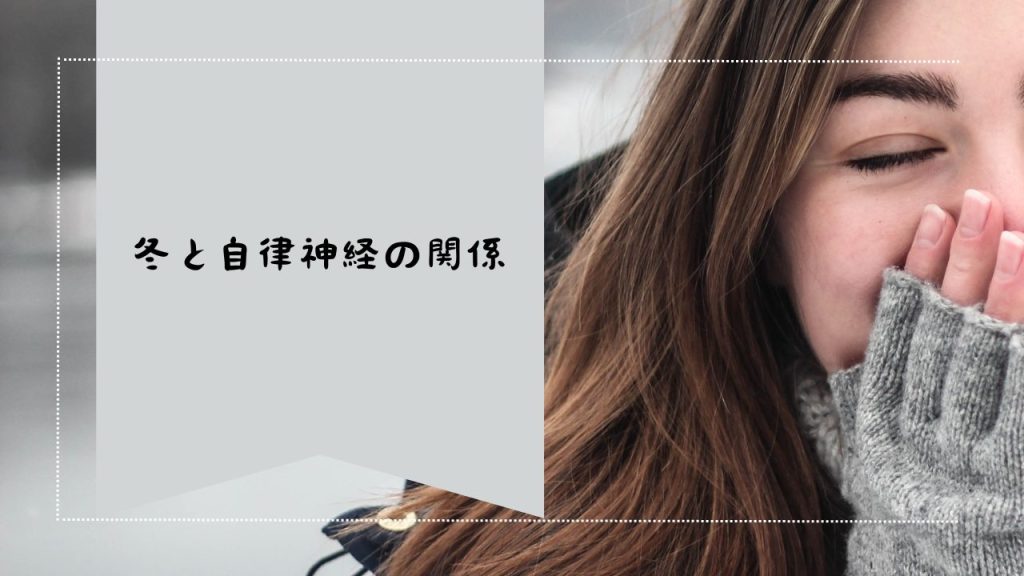冬と自律神経の関係性【BEYOND武蔵小杉】【武蔵小杉から5分】
NEWS
2024 / 12 / 23
最終更新日:2024年12月23日
冬の季節になると、寒さや日照時間の短さが原因で、体調や気分に影響を感じる人が増えます。特に、自律神経のバランスが乱れることで、さまざまな不調が起こることがあります。気分が憂鬱だと運動も中々する気になれないですよね。本記事では、自律神経と冬の関係、その乱れによる影響、そして自律神経を整えるための具体的な方法について解説します。
こちらに記事も併せてご覧ください。
https://beyond-musashikosugi.com/wp/wp-admin/post.php?post=4582&action=edit
本記事の著者

BEYOND武蔵小杉店 トレーナー
田村 勇樹
資格 NESTA PFT
BBJ 入賞経験あり
自律神経とは?
自律神経は、私たちの体の中で無意識に働く神経系の一部で、主に交感神経と副交感神経の2つから成り立っています。交感神経は「活動モード」を司り、ストレスを感じたり、集中力を高めたりする際に活発になります。一方、副交感神経は「休息モード」を担い、リラックスしたり、体を回復させたりする働きがあります。
これら2つの神経がバランスよく切り替わることで、体の調子を保っています。しかし、季節の変化や日常のストレスなどによって、このバランスが崩れると、不調が現れやすくなります。
冬が自律神経に与える影響
冬は他の季節に比べて、自律神経のバランスが乱れやすい時期です。その主な理由は以下の通りです。
1. 寒さによる体温調節への負担
気温が低くなる冬は、体が体温を保つために多くのエネルギーを使います。寒さを感じると、交感神経が優位になり、血管が収縮して体温を保とうとします。しかし、長時間寒さにさらされると、交感神経が過度に働き、自律神経のバランスが崩れることがあります。
2. 日照時間の短さ
冬は日照時間が短くなるため、体内の「セロトニン」という神経伝達物質の分泌が減少します。セロトニンは心の安定やリズムを整える役割があり、その減少は副交感神経の働きを低下させる可能性があります。これが原因で、気分が落ち込んだり、疲れやすくなったりすることがあります。
3. 運動不足
寒さや日が早く沈むことから、冬は運動量が減る傾向にあります。運動不足は血流を悪化させ、自律神経の働きに悪影響を及ぼす要因となります。また、筋肉の活動が減ることで、体全体の代謝も低下しやすくなります。
自律神経の乱れによる症状
自律神経が乱れると、以下のような症状が現れることがあります。
• 身体の不調
頭痛、肩こり、胃の不調、便秘や下痢、冷え性など。
• 精神的な不調
イライラ、気分の落ち込み、不安感、集中力の低下など。
• 睡眠の問題
寝つきが悪い、夜中に目が覚める、朝スッキリ起きられない。
こうした症状が続くと、日常生活に支障をきたすことがあります。そのため、早めに対策を講じることが大切です。
冬に自律神経を整える方法
自律神経を整えるためには、いくつかの工夫を日常生活に取り入れることが有効です。
1. 規則正しい生活を送る
毎日同じ時間に起き、同じ時間に寝るといった規則正しい生活は、自律神経のバランスを保つ基本です。また、朝起きたら太陽の光を浴びることで、体内時計をリセットし、セロトニンの分泌を促進することができます。
2. 体を温める
冷えは自律神経の乱れを助長します。暖かい服装を心がけ、手足が冷えやすい人は靴下やカイロを活用しましょう。また、入浴は体を温めるだけでなく、副交感神経を優位にする効果があります。38~40度程度のぬるめのお湯にゆっくり浸かるのがおすすめです。
3. 適度な運動をする
運動は自律神経の働きを整える上で非常に効果的です。特に、ウォーキングやストレッチなどの軽い運動は、血流を良くし、交感神経と副交感神経のバランスをとるのに役立ちます。寒い冬でも、室内でできる運動を取り入れてみましょう。
4. 食事を見直す
バランスの良い食事は、体調を整えるために欠かせません。特に冬は、ビタミンやミネラルが豊富な野菜や果物、体を温める根菜類、発酵食品などを積極的に摂るようにしましょう。また、体内でセロトニンを作る原料となるトリプトファンを含む食品(バナナ、ナッツ、魚類など)もおすすめです。
5. ストレスを溜めない
ストレスは自律神経の乱れを引き起こす最大の要因の一つです。ストレスを感じたら、自分なりのリラックス方法を見つけることが大切です。瞑想や深呼吸、アロマテラピーなどは、副交感神経を活性化する効果があります。
自律神経を整える簡単な習慣
以下のような簡単な習慣も、自律神経を整えるのに役立ちます。
以下では、先ほど紹介した自律神経を整えるための簡単な習慣について、さらに詳しく解説します。それぞれの習慣がなぜ効果的なのかを理解することで、日常生活に取り入れやすくなるはずです。
1. 毎朝3分間、深呼吸をする
深呼吸は副交感神経を活性化し、心身をリラックスさせる効果があります。朝のスタートに深呼吸を取り入れることで、自律神経のバランスを整え、心地よく一日を始めることができます。
方法:
• 朝起きたら座った状態で目を閉じ、ゆっくりと鼻から息を吸い込みます(4秒間を目安)。
• 次に、口を軽く開け、ゆっくりと息を吐きます(8秒間を目安)。
• 吸う時間より吐く時間を長くすることで、副交感神経が優位になり、リラックス効果が高まります。
• これを3分間繰り返します。
ポイント:
• 朝日を浴びながら行うと、セロトニンの分泌が促され、より高い効果が期待できます。
• 呼吸に意識を集中させることで、心を落ち着ける効果も得られます。
2. 朝食に温かいスープを取り入れる
朝は一日のスタートを切る重要な時間帯であり、自律神経のリズムを整えるためにも朝食を取ることが大切です。特に、温かいスープを取り入れることで、体を内側から温め、血流を良くして副交感神経の働きを促します。
おすすめのスープ:
• 具だくさん味噌汁
発酵食品の味噌は腸内環境を整える効果があり、自律神経にも良い影響を与えます。
• 野菜たっぷりスープ
ビタミンやミネラルが豊富な野菜を使用すると、免疫力向上にもつながります。
• ショウガ入りスープ
ショウガは体を温める効果があり、冷え性対策にも最適です。
ポイント:
• 忙しい朝でも簡単に作れるよう、前夜に仕込んでおくと続けやすくなります。
• インスタントスープを利用する場合は、塩分控えめの商品を選びましょう。
3. 就寝前にストレッチを行う
夜寝る前に軽いストレッチを行うことで、体をリラックスさせ、副交感神経を優位にします。これにより、深い眠りに入りやすくなり、自律神経の乱れを改善する効果が期待できます。
おすすめのストレッチ:
• 前屈ストレッチ
床に座り、両足を伸ばしてつま先を触るように体を前に倒します。背中や太ももの裏を伸ばすことで血流が促進されます。
• 肩甲骨回し
肩を前後にゆっくりと回し、肩甲骨をほぐします。デスクワークなどで固まった肩周りを解放するのに効果的です。
• 寝ながら腰ひねり
仰向けで寝て、片膝を反対側に倒します。腰周りの緊張をほぐし、リラックス効果を高めます。
ポイント:
• 照明を少し暗くし、静かな音楽を流すことで、よりリラックスしやすい環境を作りましょう。
• 無理に体を伸ばす必要はなく、心地よい範囲で行うことが大切です。
4. 外出時はマフラーや手袋で首や手を保護する
冬は寒さが自律神経に大きな負担をかけるため、首や手を温めることが重要です。特に首は体温調節において重要な部位であり、血流の多い場所です。
なぜ効果的か?
• 首を温めることで、全身の血流が良くなり、冷え性や肩こりの改善につながります。
• 手が冷えると交感神経が優位になりやすいため、手袋を着用して手先の冷えを防ぐことが効果的です。
ポイント:
• マフラーやスカーフは、温かいだけでなく、通気性の良い素材を選ぶと快適に使えます。
• 手袋も防風性のあるものを選ぶと、さらに冷えを防ぎやすくなります。
5. 自然を感じる時間を持つ
寒い冬でも自然に触れることで、自律神経を整える効果が得られます。特に、日中の明るい時間帯に外に出て太陽の光を浴びることが大切です。
方法:
• 公園を散歩する
• 窓辺で日光浴をする
• ベランダに出て深呼吸をする
ポイント:
• 短時間でも十分効果があります。10~15分を目安に日光を浴びることで、セロトニンの分泌が促進されます。
• 防寒対策をしっかりと行い、無理のない範囲で行いましょう。
6. 小さな習慣を積み重ねることが大切
これらの習慣を一度にすべて行おうとする必要はありません。まずは一つ、実践しやすいものから始めてみましょう。小さな習慣が積み重なることで、自律神経のバランスが徐々に整い、体と心の調子が良くなっていきます。
冬を快適に過ごすために、ぜひこれらの習慣を取り入れてみてください。
•冬を快適に過ごすために
冬は寒さや暗さなど、体と心に負担がかかる季節ですが、適切な対策を講じることで、自律神経の乱れを防ぎ、快適に過ごすことができます。日々の生活に少しずつ取り入れられる方法から始めてみましょう。
冬の季節は、自分の体を労わりながら、健康的な毎日を送る絶好の機会でもあります。無理せず、心地よい方法で、自律神経を整えることを心がけてみてください。
自律神経を整えて運動習慣も身につけていきましょう。





BEYOND武蔵小杉店では初心者で入会する人が大半なので、運動初心者の人もご安心!
https://g.page/r/CXxH5QQFxs02EBM/review
口コミはこちらから
マンツーマンで実施するので、安心・安全にトレーニングできますよ!
この機会にぜひ、運動習慣をスタートしましょう!